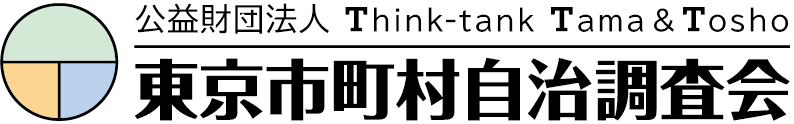住民がつくる自立した地域コミュニティの形成に関する調査研究
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:566
報告書について
調査研究の成果をまとめた報告書については、右側のリンクからご覧いただけます。
調査研究の概要
高齢社会の進展や自然災害のおそれなど、地域コミュニティでの助け合いへの期待は高まっています。その一方、自治会等「地縁型住民組織」は参加者減少等の悩みを抱えています。本調査研究は、「課題解決のためのテーマ型住民活動」を題材に、その活動が地域コミュニティ活性化につながる可能性に着目しました。
多摩・島しょ地域における地域コミュニティの現状を、地域住民組織や活動への住民の参加状況や地域の人間関係についての意識、市町村の認識状況などから調査しました。次に、全国の先進事例から、活発な住民活動を実現させている秘訣を、他にも応用できるヒントとして抽出しました。
そのうえで、住民活動を地域コミュニティ活性化につなげる秘訣を11区分に分類し、住民と自治体の双方が活性化に向けた考え方を整理できる材料を提示しました。
1.多摩・島しょ地域における地域コミュニティに関する現状と課題
(1) 多摩・島しょ住民の意識等
多摩・島しょ地域に居住する住民の地域コミュニティに関する意識や、組織・活動の状況【多摩・島しょ住民アンケート(回答者数1500人)から)】
- 地縁型住民組織へ現在加入している人は約4割
- テーマ型住民組織へ現在参加・加入している人は約1割
- 地域内に何らかの人のつながりがある人は半数以上
- 地域の人と「良好な関係」、「いざという時の助け合い」への希望が7割
- 誘われること、情報があること、必要性があることが、住民活動への参加につながりやすい
- 多くが「高齢者支援」「防犯・交通安全」「防災・災害対策」を地域の課題として挙げる
(2) 多摩・島しょ地域の市町村の地域コミュニティに関する認識
多摩・島しょ地域の市町村(39市町村)へのアンケートから
- 8割が地域コミュニティは「ある程度」以上活性化と認識
- 地縁型住民組織の課題は「参加者減少」と「担い手の高齢化等」が合わせて8割
- 「防災・災害対策」「高齢者支援」「防犯・交通安全」の課題の解決について、地域コミュニティに期待
2.9つの事例の紹介
(1) ふらっとステーション・ドリーム(横浜市戸塚区)
大規模開発分譲集合住宅団地(ドリームハイツ)では、隣接の空き店舗を活用して、気軽に集まれる居場所「ふらっとステーション・ドリーム」を住民主体で設置・運営しています。
居場所ができたことから、高齢者の見守り、健康維持、住民同士の交流、担い手にとっての生きがい等の効果が生まれ、コミュニティビジネスとしても成立しています。

(2) リビングルーム鷹巣(秋田県北秋田市)
「リビングルーム」と名付けられた取り組みは、空き店舗に地域の住民から提供された家具などを配置し住民同士の物々交換を契機に、町なかに「開かれた居間」を生みだすというアートプロジェクトです。各家々にある居間の風景を、商店街の空き店舗という異質な場所に出現させます。
それによって、そこに集う人々の新しいコミュニケーションが生まれ、多様な活動が誘発されることが期待できます。
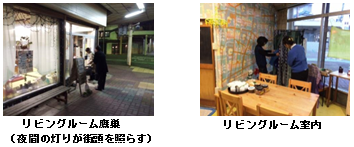
(3) 大竹ストーンアート(広島県大竹市)
巨石に市民が絵を描き、まちに設置する取り組みです。
あいさつ運動からはじまった大人と高校生の交流をきっかけにして、「大竹市暴力監視追放協議会」が青少年の健全育成を目的に2004年から実施しています。
巨石の調達から運搬・設置、作品の製作まで、様々な市民の協力を得て実施されることで、多世代の交流を生み出すとともに、今ではまちの観光資源としても活用されています。

(4) このまちにくらしたいプロジェクト(広島市西区)
中学生が自ら地域の課題を発見し、解決方法を考え、それに向けて実践するプログラム。「30年後にこのまちにくらしたいといえるまちにするために、今自分たちで何ができるか」がコンセプト。
プログラムを通じて参加生徒が地域の大人と交流する機会を設け、互いの共存意識が育まれています。
公民館の事業として実施され、住民グループ「多世代寺子屋ネットワーク」が運営をサポートしています。

(5) くさっぱら公園(東京都大田区)
住宅跡地に地域住民が運営を行う公園をつくりたいと「みんなでつくろうひろばの会」を結成し、行政に企画書を提出したことから活動が始まりました。
行政の理解と支援を受け、「利用者、行政、住民がともにつくりつづける公園」として1992年に「くさっぱら公園」開園。メンバーたちのゆるやかな関係を軸に、行政との信頼関係を築き運営されています。

(6) 明舞団地学生シェアハウス(兵庫県神戸市・明石市)
高齢化率の高い団地(県営住宅)の空き室を「学生シェアハウス」として、近隣大学の学生に住居として提供し、同時に自治会活動、地域活動への参加を求めていく取り組みです。
団地内での世代間交流が行われ、コミュニティの活力を生み出すとともに、学生にとっても貴重な社会経験を得、地域を担っていく意識を育む機会になっています。

(7) 地域共生のいえ(東京都世田谷区)
世田谷区内に家屋等を所有する住民(オーナー)自身の意思により、所有の建物を地域に開放して、地域住民の交流や子育て・高齢者支援の場、子どもの居場所等、地域の公益的なまちづくり活動の場として活用する取り組みです。「一般財団法人世田谷トラストまちづくり」が、オーナーからの相談を受け、開設に向けた支援や運営の支援、行政との連携等を行い、18の「地域共生のいえ」が実現しています。
その中の一例「岡さんのいえTOMO」では、住民が特技や個性を発揮して運営に携わり、子どもの声がにぎやかに響き、「だがしや」に近所の住民が立ち寄る場所になっています。

(8) 文京ミ・ラ・イ対話(東京都文京区)
文京区では、対話等を通じて地域の多様な主体が関わり合いながら、地域課題の解決を図る担い手を創出していく「新たな公共プロジェクト」の取り組みを実施、この一環として対話の場「文京ミ・ラ・イ対話」を実施してきました。
内容や情報発信方法の工夫により、30~40代の現役世代の多くの参加を得ています。
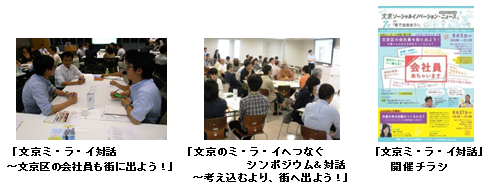
(9) 安房マネー(千葉県鴨川市、鋸南町、館山市、南房総市等)
「安房(あわ)マネー」は千葉県鴨川市等の安房地域で主に移住者の間で活用されている地域通貨です。これは、助け合い関係を仲立ちする道具であり、同時にコミュニケーションを誘うものとして機能しています。
そして会員たちのコミュニティが地域内のコミュニティネットワークへと広がり、地域住民の潜在的な力を引き出し、新たな活動(里山や棚田の保全活動、里山生活お助け隊のコミュニティビジネスなど)につながる効果を生み出しました。
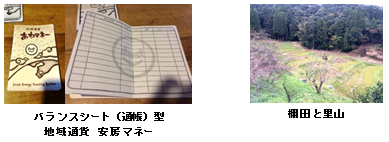
3.地域コミュニティ活性化へのヒント
事例から抽出した秘訣を、地域で活動する住民の皆さん、その活動を支援する自治体及び自治体職員の皆さんが、活動の活発化、地域コミュニティ活性化へのヒントとして応用できるよう、11の区分で整理しました。
- 多様な住民を巻き込む「道具」や「仕掛け」の活用
- 地域住民が日常的に集える「居場所」づくり、住民主体の運営
- 地域課題の顕在化・共有化(活動の動機に)
- 住民の自立性(継続活動や他との協力関係構築の基盤に)
- 活動に適した組織形態の柔軟な選択
- 住民それぞれの得意分野や人とのつながりを生かす役割分担
- 地域の担い手として若年世代・現役世代への働きかけの工夫
- 様々な住民組織の連携や役割分担、顔の見える関係づくり
- 行政との連携、企業・大学や学校との連携への働きかけ
- 行政ならではの情報収集・発信の工夫
- 行政による相談対応・後方支援やそのための連携体制づくり